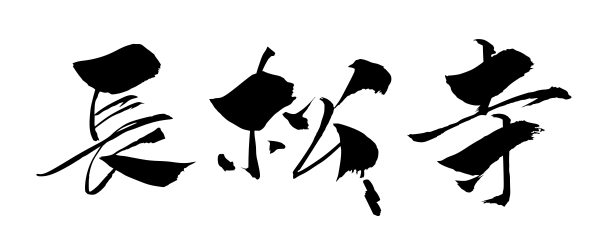- このトピックは空です。
-
投稿者投稿
-
坐禅会有志
ゲスト8月の定例坐禅会の開催は、8月3日の第一日曜日です。
投稿を日程を間違って投稿いたしました。.
訂正いたします。坐禅会有志
ゲスト8月の定例坐禅会
.
.
8月3日(日)午前6時30分から、月例坐禅会が開かれ、和尚さんと坐禅会メンバー6名、計7名で坐りました。
今月はお盆の期間と重なるため第一日曜日の開催となりました。
.
早朝から気温が高く、猛暑の中での坐禅となりました。
.
「盂蘭盆会(うらぼんえ)」
.
盂蘭盆会(うらぼんえ)とは、太陰暦7月15日を中心に7月13日から16日の4日間に行われる仏教行事のことです。仏教用語の「盂蘭盆会」の省略形として「盆」(一般に「お盆」)と呼ばれるようになりました。
.
明治期の太陽暦(新暦)の採用後、新暦7月15日に合わせると農繁期と重なって支障が出る地域が多かったため、新暦8月15日をお盆(月遅れ盆)とする地域が多くなりました。
.
盂蘭盆会は、その昔、お釈迦様のお弟子である目連尊者(もくれんそんじゃ)が、亡き母を救う話に由来しています。
.
目連尊者の母親は、子(目連尊者)を溺愛するあまり周囲の不幸に無関心だったことが原因で、餓鬼道に落ちてしまいます。
餓鬼道に落ちた母親は逆さ吊りにされ、食べるもの飲むもの全てが火となり飢えと渇きに苦しんでいました。神通力を持っていた目連尊者は、苦しむ母親を姿を目にしてお釈迦様に相談したところ、夏の修行を終えた7月15日に僧侶たちを招き、供物をささげて供養するとよい」という教えを受けます。
これに従って供養したところ、その功徳によって母親は極楽往生を遂げたと言われています。
.
なお、上記は仏教の伝来によって取り入れられた風習ですが、日本各地には古来から夏時期には祖霊を祀る習慣があったとも言われています。
こうした日本古来の風習と仏教の考えが混ざり合った結果、現在の日本におけるお盆は、家族や一族が集まり、ご先祖様や故人様を偲び、供養する行事として定着しています。
.
普段は忙しく、ご先祖様や故人様の供養までは手が回らない方々も多数いらしゃると思います。
この時期に、ご先祖様や故人様への感謝や供養の気持ちをお伝えしてはいかがでしょうか。
.
来月の月例坐禅会は、9月14日(日)午前6時30分から開催予定です。
是非、ご参加ください。
詳しくはサイトのお知らせ、および催事・行事の坐禅会の項目をご覧ください。
K.N 記坐禅会有志
ゲスト9月の定例坐禅会
.
9月14日(日)午前6時30分から、月例の坐禅会が開かれ、和尚さんと坐禅会メンバー8名、計9名で坐りました。風が心地よく、秋の始まりを感じる坐禅でした。
.
「関 南北東西活路通ず(かん なんぼくとうざい かつろつうず) 」
.
坐禅のあとの茶礼で、お部屋に掛け軸が飾ってあります。上記の禅語は、その掛け軸の内容です。和尚さんから教えていただきました。大徳寺を開山した大燈国師が公案「雲門の関」で悟りを得たときの言葉で、「関所を通過すれば、その先はどこへでも道が広がっている」という意味です。道を志している方々に好まれている言葉です。約700年前からひきつがれていく言葉に、身が引き締まる思いです。
.
次回の月例坐禅会は、10月12日(日)午前6時30分から開催予定です。
詳しくはサイトのインフォメーション、および、坐禅会の項目をご覧ください。坐禅会有志
ゲスト10月の定例坐禅会
.
10月12日(日)午前6時30分から、月例の坐禅会が開かれ、和尚さんと坐禅会メンバー6名、計9名で坐りました。お庭の銀杏も色づき、良い気候で坐禅ができました。
.
「行住坐臥(ぎょうじゅうざが)」禅は日常の全てが修行です。この言葉には、歩く・とどまる・座る・寝る、日常全てを注意深く行いなさいとの意味が込められています。私達は禅といえば坐禅のみですが、調べてみると、他のお寺では歩行禅、椅子禅、寝る禅もあるようです。ぜひ体感してみたいものです。
.
次回の月例坐禅会は、11月9日(日)午前6時30分から開催予定です。
詳しくはサイトのインフォメーション、および、坐禅会の項目をご覧ください。坐禅会有志
ゲスト11月の定例坐禅会
.
11月9日(日)午前6時30分から、月例坐禅会が開かれ、和尚さんと坐禅会メンバー6名、計7名で坐りました。
.
「腰骨を立てる(こしぼねをたてる)」
.
「腰骨を立てる」とは、腰骨を正しい位置に保ち、背骨をまっすぐにして垂直に伸ばすことです。これは、骨盤が前後に傾きすぎていたり、左右に偏ったりしていない、体の中心でバランスの取れた状態を指します。
.
坐禅の基本は、調身(ちょうしん)・調息(ちょうそく)・調心(ちょうしん)の3つと言われています。
その1番目の調身とは、身(姿勢)を調える(ととのえる)ことです。
.
体を真直ぐに保つために、筋肉を使って体の垂直を維持するのではなく、仙骨を立て、その上に背骨を積み上げ、その上に頭を載せるように姿勢を保つと全身に無駄な力が入らず、楽に姿勢を保つことが出来ます。
坐禅の指導において、姿勢を真直ぐにすることを、「腰骨を立てろ」と言われます。
.
みなさまも無理に全身に力を入れて体を真直ぐにせず、「腰骨を立てる」を意識して坐ってみてください。
.
.
来月の月例坐禅会は、12月14日(日)午前6時30分から開催予定です。
本年最後の坐禅会になります。
是非、ご参加ください。
詳しくはサイトのお知らせ、および催事・行事の坐禅会の項目をご覧ください。
K.N 記ピンファン
ゲストHello!
あなたのウェブサイトから自動的に収益を生み出す方法を考えたことはありますか?
もしまだであれば、https://profitflow.net をあなたのオンライン資産に統合することで、新しい収益源を確立できます。
このシステムは、ページ速度やデザインを損なうことなく、訪問者体験を維持しながら、あなたの収益を拡大します。
ネイティブ広告、CPM、CPA など、さまざまなマネタイズモデルと互換性があり、すべてを自動で最適化します。
主要なすべてのブラウザで動作し、SEOランキングへの影響もありません。
Best regards坐禅会有志
ゲスト12月14日(日)午前6時30分から、月例の坐禅会が開かれ、和尚さんと坐禅会メンバー6名、計7名で坐りました。冬を感じる寒さの中、今年最後の坐禅会を集中して坐ることができました。
.
「即今目前聴法底の人(そっこんもくぜんちょうぼうていの人)」(臨済録 示衆)
.
臨済禅師の弟子に向けた説法の言葉です。外や内に仏法を求める弟子に向けて、いま、ここで、教えをきいているあなた自身が仏祖そのものであると説いています。
.
いま・ここ・わたし。あらためて初心に戻って坐禅を続けていきたいと思います。
.
今年も坐禅会のご参加ありがとうございました。来年も変わらずのご参加楽しみにしております。
.
新年の月例坐禅会は、1月11日(日)午前6時30分から開催予定です。
詳しくはサイトのインフォメーション、および、坐禅会の項目をご覧ください。坐禅会有志
ゲスト1月の定例坐禅会
.
1月11日(日)午前6時30分から、本年最初の月例坐禅会が開かれ、和尚さんと坐禅会メンバー11名、計12名で坐りました。新到さん(初めて坐禅会に参加する方)1名いらっしゃいました。
.
「萬法帰一(まんぼうきいつ)」
.
お寺の書院の床の間にかかっていた、掛軸に記されていた禅語です。
一切の現象は自らの一心に他ならないのです。
.
「萬法(まんぼう)」はあらゆる存在や物事。それが「一」、ひとつだというのですから、ご飯を食べるのも、お茶を飲むのも、寝るのも起きるのも、一挙手一投足(いっきょしゅいちとうそく)がすべてひとつ。複雑に見えることも元をただせばシンプルなのだ、そこをしっかり押さえろ、ということです。
.
「一亦不守(いつもまたまもらず)」
.
「萬法帰一」に続く次の句です。
気をつけなければならないのは「萬法帰一」を大事にする心が、また執着(しゅうじゃく)になります。「一もまた守らず」、得ては捨て得ては捨て、ひとつところにとどまらずに生きていく。様々な出会いに感謝しながら、様々な別れを惜しみながら、やがて力尽きるその日まで、後ろを振り返らずに前へ前へと歩んでゆきたいものです。
.
.
来月の月例坐禅会は、2月8日(日)午前6時30分から開催予定です。
是非、ご参加ください。
詳しくはサイトのお知らせ、および催事・行事の坐禅会の項目をご覧ください。
K.N 記 -
投稿者投稿