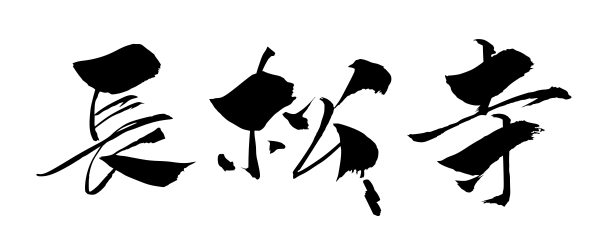- このトピックは空です。
-
投稿者投稿
-
坐禅会有志(H.O)
ゲスト4月の定例坐禅会
4月14日(日)午前6時30分から、月例の坐禅会が開かれ、和尚さまと坐禅会メンバー11名、計12名で坐りました。涼しく穏やかな気候で、坐禅に集中できました。春はよいですね。
「三人同行、必有一智(さんにんどうぎょうすればかならずいっちあり)」論語 述而第七21
三人いれば、自分の師となる人は必ずいるという意味です。坐禅会では、話さずともお互いを意識することで多くを感じとれます。
所作をみて、ふと湧いて出る気づきは得難いものです。先輩が久方ぶりに坐禅会に参加しました。またご一緒できて嬉しく思います。来月の月例坐禅会は、5月12日(日)午前6時30分から開催予定です。詳しくはサイトのお知らせ、および催事・行事の坐禅会の項目をご覧ください。
坐禅会有志
ゲスト5月12日(日)午前6時30分から、月例の坐禅会が開かれ、和尚さんと坐禅会メンバー11名、計12名で坐りました。新到さん(初めて坐禅会に参加する方)2名いらっしゃいました。
5月らしいさわやかな気候で、坐禅をするには最適な朝でした。
「人間の好時節(じんかんのこうじせつ)」
春、百花あり。
秋、月あり。
夏、涼風あり。
冬、雪あり。
もし、閑事の心頭に挂ることなくんば、すなわちこれ人間の好時節。これは、禅門で有名な「無門関」にある偈(詩)です。
春は百花爛漫として咲き綻び、秋は月が美しい。
夏は涼しい風が吹き、冬はすがすがしく雪が降る。
つまらぬことにあれこれ思い煩うことがなかったら、春夏秋冬、いつでも人間にとって好時節である、というのである。
春夏秋冬、それぞれ趣があって、誠に結構な四季の移り変わりですが、それなのに嘆き悲しみ瞋り、悩むのは一体どういうわけでしょう。
それは、余計な分別、要らざる計らいがこころの中にモヤモヤしているからで、これさえなければ春夏秋冬いつでもすがすがしい好時節であります。皆さま、坐禅にて、心の中のモヤモヤを整理してみませんか。
これからは、暑い季節となります。当坐禅会では、短パンでの参加はご遠慮いただいております。上着は半袖でかまいませんが、タンクトップ、ランニングシャツ等の露出度の高い服装はご遠慮ください。
来月の月例坐禅会は、6月9日(日)午前6時30分から開催予定です。
是非、ご参加ください。
詳しくはサイトのインフォメーション、および、坐禅会の項目をご覧ください。
K.N 記坐禅会有志
ゲスト6月の定例坐禅会
6月9日(日)午前6時30分から、月例の坐禅会が開かれ、和尚さんと坐禅会メンバー12名、計13名で坐りました。新到さん(初めて坐禅会に参加する方)1名いらっしゃいました。
6月にしては、涼しい朝でした。湿度が高かったのですが、坐禅をするには最適な朝でした。
「己事究明(こじきゅうめい)」
坐禅は何のためにするのでしょうか。あえて言葉にするならば、仏法を体得するためです。そうすることで、「自分とは何者か」「なぜ自分は生まれてきたのか」などという人生の根源的な問題を解こうとしているのです。それは、「己事究明」と言い換えてもよいでしょう。禅の修行は、「己事究明」そのものの道でもあります。
己事究明とは、簡単に言えば「本来の自分を追究すること」です。「本来の自分」と言葉で言うのは簡単ですが、「自分はこういう人間だ」「こういう生き方をしてきた」などと言葉で表現できるうちは、真の己事究明ではありません。文字や言葉で表現できる「己事」を超えたときに真の「究明」になるのです。
坐禅にて「本来の自分」を見つめ直してはいかがでしょうか。
来月の月例坐禅会は、7月14日(日)午前6時30分から開催予定です。
是非、ご参加ください。
詳しくはサイトのインフォメーション、および、坐禅会の項目をご覧ください。
K.N 記坐禅会有志
ゲスト7月の定例坐禅会
7月14日(日)午前6時30分から、月例の坐禅会が開かれ、和尚さまと坐禅会メンバー9名、計10名で坐りました。梅雨明け前の雨音を聞きながら、落ち着いた坐禅ができました。
「一滴潤乾坤(いってき、けんこんをうるおす )」
北宋の時代の景徳伝灯録にある、ひとしずくの水が天地を潤すという禅語です。達磨大師の教えを一滴のしずくにたとえ、その一滴が秘めている力を表現しています。最初の一滴に想いを馳せる解釈が好きです。
来月の月例坐禅会は、8月11日(日)午前6時30分から開催予定です。詳しくはサイトのお知らせ、および催事・行事の坐禅会の項目をご覧ください。
坐禅会有志
ゲスト8月の定例坐禅会
8月11日(日)午前6時30分から、月例の坐禅会が開かれ、和尚さまと坐禅会メンバー6名、計7名で坐りました。お盆休みの中、初めての方が2名こられました。
厳しい暑さですが、今日はお堂に風も入り、夏の終わりを感じる坐禅ができました。来月は少し涼しくなりそうです。
夏の坐禅で次の言葉が浮かんできました。「心頭を滅却すれば 火も亦涼し」(しんとうをめっきゃくすれば、ひもまたすずし)
子供のときに覚えた言葉です。
もともとは中国の唐の詩人、杜筍鶴(とじゅんかく)の漢詩「夏日題悟空上人院」の一文です。
日本では臨済宗妙心寺派の禅僧、快川紹喜(かいせんじょうき)禅師の逸話が有名です。
戦国時代に織田信長の軍勢は甲府の恵林寺を焼き討ちしました。
快川禅師は燃えさかる山門でこの言葉とともに。。
この逸話は涼しくなります。来月の月例坐禅会は、9月8日(日)午前6時30分から開催予定です。
詳しくはサイトのお知らせ、および催事・行事の坐禅会の項目をご覧ください。坐禅会有志
ゲスト9月の定例坐禅会
.
9月8日(日)午前6時30分から、月例の坐禅会が開かれ、和尚さんと坐禅会メンバー11名、計12名で坐りました。
.
残暑厳しい朝でしたが、風が吹くと涼しさを感じられ、境内にも虫の鳴き声が響き、秋を感じる朝でした。
.
「驀直去(まくじきこ)」
.
蒙古襲来時、無学祖元禅師が鎌倉幕府八代目の執権・北条時宗に授けた教えです。
無学祖元禅師は中国から円覚寺に来ていた禅僧です。
.
「驀直去」とはまっしぐらに一直線に突き抜けろということであります。避けるな、逃げるな。小手先細工では国を救うことはできない、無学祖元はそれを時宗に教えたかったのです。苦しかったら苦しみの中に浸りきって、それを突き抜けろと言っているのです。時宗は若かったから、大事を避けようとしました。それに対して、無学祖元はビシッと喝を食らわしたわけです。
迷った時、臆病になった時、壁に突き当たった時は、自分を信じて、まずやってみる。常にそうありたいものです。
.
来月の月例坐禅会は、10月13日(日)午前6時30分から開催予定です。
是非、ご参加ください。
詳しくはサイトのインフォメーション、および、坐禅会の項目をご覧ください。
K.N 記坐禅会有志
ゲスト10月の定例坐禅会
*
10月6日(日)午前6時30分から、月例の坐禅会が開かれ、和尚さまと坐禅会メンバー5名、計6名で坐りました。今月は都合により第1週の開催です。涼しい時節で、気持ち良く坐れました。
*
「無心(むしん)」
*
禅語では、無心は心を無くすことではありません。一切の妄念を離れたありのままの心のことを指します。
*
家や職場では常になにかを考えて、心は忙しく動いてます。坐禅では息を数えることに意識を向けます。すると次第に心の動きも穏やかになり、執着ない自然な心が現れてきます。これが無心です。仏は心の中にいると聞きました。坐禅でいつか出会いたいなと思っています。
*
来月の月例坐禅会は、11月10日(日)午前6時30分から開催予定です。
詳しくはサイトのお知らせ、および催事・行事の坐禅会の項目をご覧ください。坐禅会有志
ゲスト11月の定例坐禅会
.
11月10日(日)午前6時30分から、月例の坐禅会が開かれ、和尚さんと坐禅会メンバー13名、計14名で坐りました。新到さん(初めて坐禅会に参加する方)3名いらっしゃいました。
.
初冬らしい冷え込みで、寒さを感じる朝でした。
.
「日日是好日(にちにちこれこうにち)」
.
お寺の床の間にかかっていた掛け軸の文言です。
.
唐代の禅僧である雲門文偃和尚の有名な言葉です。その語の通りに読めば、「毎日は、良い日である。」という意味です。
人生においては、「良い」か「悪い」ではなく、如何にして「好ましい」日に出来るかと、前向きに考えることが大切です。
.
今日の一日は二度と来ないかけがえのない一時であり、全身全霊をこめて生きることが好日を見出すことに繋がります。 自らの生き方に好日を見い出すことが大切である、ということなのでしょう。
.
来月の月例坐禅会は、12月8日(日)午前6時30分から開催予定です。
是非、ご参加ください。
詳しくはサイトのインフォメーション、および、坐禅会の項目をご覧ください。
K.N 記坐禅会有志
ゲスト12月の定例坐禅会
.
12月8日(日)午前6時30分から、月例の坐禅会が開かれ、和尚さんと坐禅会メンバー12名、計13名で坐りました。冬らしい寒さで坐禅に集中できました。
.
仏教の宗派についてご存じですか?
.
日本では、奈良時代から鎌倉時代にかけて仏教が発展してきました。
奈良時代は大学のように僧侶が学び、平安時代は密教が現世利益を願った貴族へ広がり、鎌倉時代はわかりやすい行為として武士や庶民へ広がり、多くの宗派があります。
.
宗派によって大事にしている修行が異なるので、それぞれのお寺で雰囲気が違うことに気づきます。
私たちがお世話になっている長松寺は鎌倉時代に成立した臨済宗のお寺です。
坐禅を大事にしています。今年も坐禅会のご参加ありがとうございました。
.
新年の月例坐禅会は、1月12日(日)午前6時30分から開催予定です。
詳しくはサイトのインフォメーション、および、坐禅会の項目をご覧ください。坐禅会有志
ゲスト1月の定例坐禅会
.
1月12日(日)午前6時30分から、本年最初の月例坐禅会が開かれ、和尚さんと坐禅会メンバー5名、計6名で坐りました。
.
厳しい冷え込みで、寒さに震えながらの坐禅となりました。。
.
「心頭滅却すれば火もまた涼し(しんとうめっきゃくすればひもまたすずし)」
.
人間というのは無念無想の境地に至ったならば、火さえも涼しく感じられるようになるということであります。どのような困難や苦難であっても、それを超越した境地に入ったならば何でもないことになるということであります。いかなる苦痛であっても心の持ち方次第でしのぐことができるということであります。
.
坐禅に集中し、無になれば、寒さも超越できる。そのような境地に少しでも近づきたいものです。
.
来月の月例坐禅会は、2月9日(日)午前6時30分から開催予定です。
是非、ご参加ください。
詳しくはサイトのお知らせ、および催事・行事の坐禅会の項目をご覧ください。
K.N 記坐禅会有志(H.O)
ゲスト2月の定例坐禅会
.
2月9日(日)午前6時30分から、月例の坐禅会が開かれ、和尚さんと坐禅会メンバー6名、計7名で坐りました。冷えたお堂で2月らしい寒さの中、集中して坐禅ができました。
.
「放下著」 (ほうげじゃく)
.
中国の唐の高僧、趙州従諗(じょうしゅうじゅうしん)が、弟子に答えた言葉です。「 著 じゃく 」は命令の 助辞 で放下の意味を強めています。つまり「捨てなさい」ということです。
.
捨てるには、何を捨てるのか自分の執着に気づくことが必要です。禅の修行道場では生活の役割・時間・量が厳密に決まっているそうです。修行の中で、自分の時間もなく不合理で理不尽で不満に思ってはじめて、自分の執着に気づくそうです。
.
執着に気づき、放下して、解釈して、心を整える。
.
僕らも普段の生活で忙しいですが、何に執着しているかに気づき「放下」することで、新しい気づきを得られるかもしれません。
.
次回の月例坐禅会は、3月9日(日)午前6時30分から開催予定です。
詳しくはサイトのインフォメーション、および、坐禅会の項目をご覧ください。坐禅会有志
ゲスト3月の定例坐禅会
.
3月9日(日)午前6時30分から、月例坐禅会が開かれ、和尚さんと坐禅会メンバー9名、計10名で坐りました。新到さん(初めて坐禅会に参加する方)1名いらっしゃいました。
.
3月にしては、寒い朝でしたが、春を感じる気候でした。
.
「直指人心 見性成仏(じきしにんしん けんしょうじょうぶつ)」
.
真理は自己の心の外にあるのではなく、自己の心のなかにこそ発見される、真理であるその自己の本性をみるならば、仏となることができる、という意味です。
.
私たちは何かを求めるというと、他にいろいろ求め、彷徨いますが、禅は自分の心に問いかけ自分の本当の姿を看て取れ、という訳です。
本当の自分、すなわち仏性を直接的端的に把握することをいう訳です。
皆さま、坐禅にて、本当の自分を発見してみてはいかがでしょうか。
.
来月の月例坐禅会は、4月13日(日)午前6時30分から開催予定です。
是非、ご参加ください。
詳しくはサイトのお知らせ、および催事・行事の坐禅会の項目をご覧ください。
K.N 記坐禅会有志
ゲスト4月の定例坐禅会
.
4月13日(日)午前6時30分から、月例の坐禅会が開かれ、和尚さんと坐禅会メンバー10名、計11名で坐りました。やや肌寒いですが、春を感じながら集中して坐禅ができました。
.
春來草自生(はるきたりてくさおのずからしょうず)
.
景徳伝灯録の「兀然無事坐 春來草自生」からの言葉で「ただじっと坐禅をせよ。そのときになれば悟りの境地は自然に訪れる」という意味です。
.
あらためて坐禅を考えてみると、草木の在り方に似ています。草木は動かず力をためて春の訪れを待ちます。条件が整うと芽吹きます。坐禅も動かず、条件がそろうと新たな気付きを得ます。
.
坐っているときに雑念がでたら草木をイメージするとよいかもしれませんね。
.
次回の月例坐禅会は、5月11日(日)午前6時30分から開催予定です。
詳しくはサイトのインフォメーション、および、坐禅会の項目をご覧ください。坐禅会有志
ゲスト5月の定例坐禅会
.
.
5月11日(日)午前6時30分から、月例坐禅会が開かれ、和尚さんと坐禅会メンバー12名、計13名で坐りました。新到さん(初めて坐禅会に参加する方)1名いらっしゃいました。
.
暑くなく、寒くなく、坐禅をするには最適の気候でした。
.
「本来無一物(ほんらいむいちもつ)」
.
事物はすべて本来空(くう)であるから、執着すべきものは何一つないという意味になります。
.
この言句は中国禅宗六祖(ろくそ)の大鑑慧能禅師(だいかんえのうぜんし)(638~713)のものと言われており、『六祖壇経』に次のような偈(漢詩)が載せられています。
.
菩提本樹無(ぼだいもとじゅな)し、明鏡亦台(めいきょうまただい)に非(あら)ず。本来無一物、何(いず)れの処(ところ)にか塵埃(じんあい)を惹(ひ)かん。
.
ここでの本来無一物とは、「私達人間の身心の生まれたままの本性は元々ピュアなもので菩提だの明鏡だのといった言葉で解説したり、思慮で推し量ろうとするまでもない」といった意味です。慧能という人物はこの純粋さをずっと保ち続けていた稀有(けう)の人だったので六祖と成り得たのでしょう。
.「本来」は「もともと」や「本質的に」という意味、「無一物」は「何一つない」という意味です。禅宗では、人間は生まれながらにして何一つ持っておらず、全ては本来「空(くう)」の状態であると考えられています。
.
物欲や地位、名誉など、人間が執着する対象を否定するものではありません。執着が苦悩を生むことを指摘し、執着を手放すことによって心の平静を得られると説きます。
.
私たちは、自我をつくり、相対分別をしつづけ、あらゆるものを所有し、所有したものに執著しつづけて生きています。如何に多くの財産やものを所有したとしても、死滅することにより、最終的に私のものは何一つとしてないことに目覚めなくてはなりません。
また、自我にまみれた私からも私を開放しなくてはなりません。
本来、仏としての自己に出会うこと。それが私たちが執着を手放す方法です。
坐禅にて本来の自己に気付く努力をしてみませんか。
.
来月の月例坐禅会は、6月8日(日)午前6時30分から開催予定です。
是非、ご参加ください。
詳しくはサイトのお知らせ、および催事・行事の坐禅会の項目をご覧ください。
K.N 記坐禅会有志
ゲスト7月の定例坐禅会
.
.
7月13日(日)午前6時30分から、月例坐禅会が開かれ、和尚さんと坐禅会メンバー8名、計9名で坐りました。新到さん(初めて坐禅会に参加する方)2名いらっしゃいました。
.
この時期にしては涼しく、快適に坐禅をすることができました。
.
「一寸坐れば一寸の仏(いっすんすわれば いっすんのほとけ)」
.
坐禅をする時に線香を立てます。「坐る」は坐禅を表し、一寸とは線香が一寸(3㎝)燃える時間のことです。短い間でも、坐禅をして心を調えれば その間は元々生まれたときから頂いている仏様のような尊い心になる。という意味です。坐禅は仏教の修行法のひとつです。坐禅には、以下のような効果が期待できます。
.
心の安定: 坐禅を通じて心を整えることで、ストレスや不安を軽減し、精神的な安定を得られます。
.
集中力の向上: 「今」に集中する禅の教えは、仕事や学習における集中力を高める助けとなります。
.
また、坐禅をするときの呼吸には、脳内神経伝達物質のひとつ「セロトニン」の分泌を促す効果があります。セロトニンは別名「幸せホルモン」とも呼ばれていて、精神の安定や感情のコントロールに大きく関わっています。何度も坐禅を繰り返せば、セロトニンの分泌が促されている状態が通常になっていきます。すると集中力もアップしますし、ストレスの影響も受けにくくなります。うつ病の予防にもつながるといわれています。セロトニンの分泌量が増えると、ストレスが軽減されリラックスできます。不眠の解消にもつながり、ぐっすり眠れるようになります。自律神経のバランスも整うので、アンチエイジングも期待できるでしょう。
.
坐禅をしてもすぐに効果が表れるとは限りません。
一寸坐れば 一寸の仏
一日坐れば 一日の仏
一年坐れば 一年の仏
.
どんなに短い時間でも 坐禅をして心を調えることで 自分の仏の心を実感することができるのです。
.
少しの時間でも坐れば、その分だけ心が清らかになり、磨かれ、それだけ仏の姿に近づきます。これを毎日積みかさねますと、いつの間にか大きな仏性になるというのです。
.
私たちには、パソコンやスマホのようにリセットボタンはありません。
自分の心を見つめなおし、心をリフレッシュすることが時には必要です。
坐禅にて、心を整え、日常生活の心の安定を図ってみてはいかがでしょう。
.
来月の月例坐禅会は、8月8日(日)午前6時30分から開催予定です。
お盆の期間と重なるので、8月は第一日曜日に開催が変更されます。
是非、ご参加ください。
詳しくはサイトのお知らせ、および催事・行事の坐禅会の項目をご覧ください。
K.N 記 -
投稿者投稿